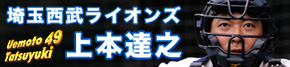гҒӮгӮҢгҒӢгӮүдёҖе№ҙеҫҢгҒ®2012е№ҙ3жңҲ11ж—ҘгҖӮ
гҒӮгҒӘгҒҹгҒҜдҪ•гӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҒӢпјҹ
гҒҝгӮ“гҒӘгҒҢж’®гҒЈгҒҹж—ҘеёёгӮ’гҒӨгҒӘгҒҺеҗҲгӮҸгҒӣгҒҹгӮүгҖҒдёҖжң¬гҒ®зү№еҲҘгҒӘжҳ з”»гҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

INTRODUCTION
|
|
|
ж—ҘеёёгӮ’з”ҹгҒҚгӮӢдәәгҖ…гҒ®е§ҝгҒ«гҖҒгҒ©гҒҶгҒ—гҒҰгҒ“гӮ“гҒӘгҒ«гӮӮеҝғгҒҢеӢ•гҒӢгҒ•гӮҢгӮӢгҒ®гҒ гӮҚгҒҶгҖӮ 2010е№ҙ7жңҲ24ж—ҘгҖҒгҒӮгҒӘгҒҹгҒ®ж—ҘеёёгҒ®1гӮігғһгӮ’ж’®еҪұгҒ—гҒҰйҖҒгҒЈгҒҰгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ гғӘгғүгғӘгғјпјҶгғҲгғӢгғјгғ»гӮ№гӮігғғгғҲе…„ејҹгҒ®гҒқгҒ®е‘јгҒігҒӢгҒ‘гҒ«гҖҒдё–з•ҢдёӯгҒӢгӮүеӢ•з”»гҒҢжҠ•зЁҝгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮдё–з•ҢеҲқгҒ«гҒ—гҒҰең°зҗғиҰҸжЁЎгҒ®дёҖеӨ§гғ—гғӯгӮёгӮ§гӮҜгғҲгҖҺLIFE IN A DAYгҖҸгҖӮгҒӘгӮ“гҒ§гӮӮгҒӘгҒ„1ж—ҘгӮ’ж…ҲгҒ—гӮҖгӮҲгҒҶгҒӘгҖҒгҒІгҒЁгҒӨгҒІгҒЁгҒӨгҒ®жҳ еғҸгҒҢз№ӢгҒҢгӮҠ1жң¬гҒ®жҳ з”»гҒЁгҒӘгҒЈгҒҹжҷӮгҖҒеҸӮеҠ гҒ—гҒҹдәәгҖ…гҒ®жғігҒ„гҒҜгҒІгҒЁгҒӨгҒ«гҒӘгӮҠгҖҒжҷӮгҒ«зҫҺгҒ—гҒҸгҖҒгғҰгғјгғўгғ©гӮ№гҒ§ж„ҹеӢ•зҡ„гҒӘгҖҒз”»жңҹзҡ„гҒӘгӮҪгғјгӮ·гғЈгғ«гғ»гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгғ»гғ гғјгғ“гғјгҒҢиӘ•з”ҹгҒ—гҒҹгҖӮ гҒқгҒ—гҒҰ2012е№ҙ3жңҲ11ж—ҘгҖӮж—Ҙжң¬гҒҢгҖҒгҒқгҒ—гҒҰдё–з•ҢгҒҢиҮӘ然гҒ®и„…еЁҒгҒ«жҷ’гҒ•гӮҢгҒҹвҖңгҒӮгҒ®ж—ҘвҖқгҒӢгӮү1е№ҙгҖӮдәәгҖ…гҒҜгҒ©гӮ“гҒӘ24жҷӮй–“гӮ’йҒҺгҒ”гҒ—гҒҹгҒ®гҒ гӮҚгҒҶгҒӢгҖӮгҒқгӮҢгӮ’иЁҳйҢІгҒ«ж®ӢгҒҷгҒ“гҒЁгҒҢгҖҒгҒӮгҒ®ж—ҘгӮ’еҝҳгӮҢгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҖҒгҒӮгҒ®ж—ҘгӮ’еҝғгҒ«еҲ»гӮҖгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҖӮгҒқгӮ“гҒӘжғігҒ„гҒ®гӮӮгҒЁгҖҒгғӘгғүгғӘгғјгғ»гӮ№гӮігғғгғҲзҺҮгҒ„гӮӢгӮ№гӮігғғгғҲгғ»гғ•гғӘгғјгҒЁгғ•гӮёгғҶгғ¬гғ“гҒ®е…ұеҗҢгғ—гғӯгӮёгӮ§гӮҜгғҲгҖҺJAPAN IN A DAYгҖҖ[гӮёгғЈгғ‘гғі гӮӨгғі гӮў гғҮгӮӨ] гҖҸгҒҢеӢ•гҒҚеҮәгҒ—гҒҹгҖӮ 2012е№ҙ3жңҲ11ж—ҘгҒ«ж’®еҪұгҒ•гӮҢйӣҶгӮҒгӮүгӮҢгҒҹгҖҒдё–з•Ң12гӮ«еӣҪгҖҒ8000жң¬гҖҒ300жҷӮй–“гӮӮгҒ®еӢ•з”»гҒҹгҒЎгҒҢжҸҸгҒҚеҮәгҒҷгҖҒгҒӮгӮӢпј’пј”жҷӮй–“гҒ®зү©иӘһгҖӮ 1жӯігҒ®иӘ•з”ҹж—ҘгӮ’иҝҺгҒҲгҒҹеҘігҒ®еӯҗгҖҒеҲқгӮҒгҒҰйҒ гҒҸгҒ®е…¬ең’гҒҫгҒ§еҮәгҒӢгҒ‘гҒҹзҲ¶еӯҗ家еәӯгҒ®иҰӘеӯҗгҖҒе©ҡ姻еұҠгӮ’жҸҗеҮәгҒҷгӮӢгӮ«гғғгғ—гғ«гҖҒеҮәз”ЈгҒ®ж—ҘгӮ’иҝҺгҒҲгҒҹеӨ«е©ҰгҖҒвҖ•вҖ•гҒқгҒ®ж—ҘгҒҢиЁҳеҝөж—ҘгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹдәәгҖ…гҒ®е§ҝгҖӮ е®ўгҒЁз¬‘гҒ„еҗҲгҒҶй…’еұӢгҒ®еә—дё»гҖҒеҘігҒ®еӯҗгҒҢеҒ¶з„¶гӮ«гғЎгғ©гҒ§жҚүгҒҲгҒҹе°ҸгҒ•гҒӘе°ҸгҒ•гҒӘй»„иүІгҒ„иҠұгҖҒж—Ҙжң¬еҗ„ең°гҒ§иЎҢгӮҸгӮҢгҒҹгғһгғ©гӮҪгғійўЁжҷҜгҖҒвҖ•вҖ•гҒӮгӮҠгҒөгӮҢгҒҹдёҖж—ҘгӮ’ж…ҲгҒ—гӮҖгӮҲгҒҶгҒӘжҳ еғҸгҒҹгҒЎгҖӮ гҒқгҒ—гҒҰйңҮзҒҪгҒ®иө·гҒ“гҒЈгҒҹ14жҷӮ46еҲҶгҖӮж—Ҙжң¬дёӯгҒҢгҖҒгҖҢй»ҷгҒЁгҒҶгҖҚгҒ®еЈ°гҒЁе…ұгҒ«гӮ¬гғ¬гӮӯгӮ„жө·гҒ«иҠұгӮ’дҫӣгҒҲгҖҒзҘҲгӮҠгӮ’жҚ§гҒ’гӮӢгҖӮгҒқгҒ—гҒҰгҒӮгӮӢз”·жҖ§гҒҜгӮ«гғЎгғ©гӮ’еүҚгҒ«гҒ—гҖҒ家ж—ҸгӮ„家гӮ’еӨұгҒ„гҒӘгҒҢгӮүгӮӮгҖҒгҒ“гӮҢгҒӢгӮүгӮӮеј·гҒҸжӯ©гӮ“гҒ§гҒ„гҒҸгҒЁгҒ„гҒҶзӢ¬зҷҪгӮ’гҒҷгӮӢгҖӮвҖ•вҖ•з§ҒгҒҹгҒЎгҒҢжұәгҒ—гҒҰеҝҳгӮҢгӮӢдәӢгҒ®гҒӘгҒ„гҖҒжғігҒ„гҖӮ гҒ“гӮҢгӮүе…ЁгҒҸеҲҘгҖ…гҒ®гӮЁгғ”гӮҪгғјгғүгҒҢгҒІгҒЁгҒӨгҒ«гҒӨгҒӘгҒҢгӮҠгҖҒгӮ№гғҲгғјгғӘгғјгҒЁгҒӘгӮҠгҖҒдәәгҖ…гҒ®жғігҒ„гҒҜеёҢжңӣгҒ«жәўгӮҢгҒҹгҖҒгҒІгҒЁгҒӨгҒ®зү©иӘһгӮ’зҙЎгҒҺеҮәгҒҷгҖӮ гҒӮгӮҠгҒөгӮҢгҒҹж—ҘеёёгҒҢгҖҒгҒӘгҒңгҒ“гӮ“гҒӘгҒ«гӮӮж„ӣгҒҠгҒ—гҒ„гҒ®гҒӢвҖ•вҖ•гҖҒгҒӮгӮҠгҒөгӮҢгҒҹж—ҘеёёгҒ«гҖҒгҒӘгҒңгҒ“гӮ“гҒӘгҒ«гӮӮж¶ҷгҒҷгӮӢгҒ®гҒӢвҖ•вҖ•гҖӮ гҒ“гӮҢгҒҜгҖҒгҒқгҒ®ж—ҘгӮ’з”ҹгҒҚгҒҹдәәгҖ…гҒ®е§ҝгҖӮгҒқгҒ—гҒҰгҖҒгҒ„гҒҫгӮ’з”ҹгҒҚгӮӢгҖҒз§ҒгҒҹгҒЎгҒ®зү©иӘһгҖӮ |
STORY & BEHIND THE SCENES
|
|
|
2012е№ҙ3жңҲ11ж—ҘгҖҒж—Ҙжӣңж—ҘгҖӮ зөӮйӣ»гҒҢеҺ»гӮҠгҖҒеӨңгҒҢжӣҙгҒ‘гҖҒгҒқгӮҢгҒ§гӮӮйғҪдјҡгҒ®иЎ—гҒҜзң гӮүгҒӘгҒ„гҖӮиӢҘиҖ…гҒҹгҒЎгҒҜжңқгҒҢжқҘгӮӢгҒ“гҒЁгҒӘгҒ©еҝҳгӮҢгҒҹгҒӢгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«й…’гӮ„йҹіжҘҪгҒ«иҲҲгҒҳгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ гӮ„гҒҢгҒҰеӨӘйҷҪгҒҢжҳҮгӮҠгҖҒе…үгҒҢйҷҚгӮҠжіЁгҒҺе§ӢгӮҒгӮӢгҖӮгғ“гғ«гҒ«гҖҒгӮ№гӮ«гӮӨгғ„гғӘгғјгҒ«гҖҒгҒқгҒ—гҒҰгҒҹгҒҸгҒ•гӮ“гҒ®е‘ҪгӮ’гҒ®гҒҝиҫјгӮ“гҒ жқұеҢ—гҒ®жө·гҒ«гӮӮв”Җв”ҖгҖӮ гӮ«гғЎгғ©гӮ’гҒҳгҒЈгҒЁиҰӢгҒӨгӮҒгӮӢиөӨгҒЎгӮғгӮ“гҖӮгҒӨгҒ¶гӮүгҒӘзһігҒҢж„ӣгӮүгҒ—гҒҸгҖҒй ¬з¬‘гҒҝгӮ’гҒҹгҒҹгҒҲгҒҹеҸЈе…ғгҒҢгҖҒд»ҠгҒ«гӮӮдҪ•гҒӢгӮ’гҒ—гӮғгҒ№гӮҠеҮәгҒ—гҒқгҒҶгҒ гҖӮ1е№ҙеүҚгҒ®3.11гҖҒиөӨгҒЎгӮғгӮ“гҒҜгҒҫгҒ гҖҒжҜҚиҰӘгҒ®гҒҠи…№гҒ®дёӯгҒ«гҒ„гҒҹгҖӮгҒӮгҒ®ж—ҘгҖҒиғҺеӢ•гҒ§гҒ—гҒӢе‘ҪгӮ’зўәгҒӢгӮҒгӮүгӮҢгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹеӯҗгҒ©гӮӮгҒҢгҖҒгҒ„гҒҫзӣ®гҒ®еүҚгҒ§з¬‘гҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮд»ҠгҒ§гҒҜиӮҢгҒ®жё©гӮӮгӮҠгӮ„еЈ°гҒ§гҖҒжҲҗй•·гӮ’зўәгҒӢгӮҒгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҒ®гҒ гҖӮ зҲ¶иҰӘгҒ®иҮӘи»ўи»ҠгҒ®гғҒгғЈгӮӨгғ«гғүгӮ·гғјгғҲгҒ«д№—гӮҠиҫјгӮҖз”·гҒ®еӯҗгҖӮгғҳгғ«гғЎгғғгғҲгӮ’гҒӢгҒ¶гҒЈгҒҰгҖҒжҜӣеёғгӮ’гҒӢгҒ‘гҒҰгҖҒеҜ’гҒ•еҜҫзӯ–гӮӮдёҮе…ЁгҖӮйҒ“и·ҜгӮ’иө°гӮҠгҖҒйҡҺж®өгӮ’дёҠгӮҠгҖҒзҲ¶гҒҜеӨ§еӨүгҒ гҖӮзҲ¶еӯҗ家еәӯгҒ®ж—Ҙжӣңж—ҘгҖӮд»Ҡж—ҘгҒҜе°‘гҒ—йҒ гҒҸгҒ«гҒӮгӮӢе…¬ең’гҒёеҲқгӮҒгҒҰеҮәгҒӢгҒ‘гӮӢгҒ®гҒ гҖӮдёҖз”ҹжҮёе‘ҪгҒ«иҮӘи»ўи»ҠгӮ’гҒ“гҒҗзҲ¶гҒ«гҖҒз”·гҒ®еӯҗгҒҢи©ұгҒ—гҒӢгҒ‘гӮӢгҖӮеғ•гҒҢеӨ§гҒҚгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгӮүгҖҒгҒҠзҲ¶гҒ•гӮ“гӮ’д№—гҒӣгҒҰгҒ“гҒ„гҒ§гҒӮгҒ’гӮӢгҖҒгҒЁгҖӮгҖҢгҒқгӮҢгҒҜгғ©гӮҜгғҒгғігҒ гҒӘгҖҚгҒЁзҲ¶гҒ®еЈ°гҒҜејҫгӮҖгҖӮ жҳ”гҒӘгҒҢгӮүгҒ®й…’еұӢгҖӮеҲқиҖҒгҒ®еә—дё»гҒҢгҒқгӮҚгҒ°гӮ“гӮ’гҒҜгҒҳгҒҚгҖҒеҰ»гҒҢе®ўгӮ’зӣёжүӢгҒ«з¬‘гҒҶгҖӮе®ўгҒҢгӮ«гӮҰгғігӮҝгғјгӮ’еүҚгҒ«з«ӢгҒЈгҒҹгҒҫгҒҫгӮҜгӮӨгғғгҒЁгӮігғғгғ—й…’гӮ’гҒӮгҒҠгҒЈгҒҰгҒҜгҖҒеё°гҒЈгҒҰгҒ„гҒҸгҖӮеҢ—д№қе·һзӢ¬зү№гҒ®ж–ҮеҢ–гҒЁиЁҖгӮҸгӮҢгӮӢвҖңи§’жү“гҒЎвҖқгҒ®йўЁжҷҜгҒ гҖӮгҒ“гҒ“гҒҜгҖҒжқұеҢ—гҒӢгӮү1000гӮӯгғӯгҒ»гҒ©йӣўгӮҢгҒҹд№қе·һгҒ®ең°гҖӮгҒқгӮ“гҒӘйҒ гҒҸгҒ§дҪ•гҒҢеҮәжқҘгӮӢгҒ®гҒӢгҒЁгҖҒж’®еҪұиҖ…гҒҜиҖғгҒҲгӮӢгҖӮеҪјгҒҜй…’еұӢгҒ®еә—дё»гҒЁд»–дәәгҒ§гҒӮгӮӢе®ўгҒЁгҒ®еҝғгҒ®и§ҰгӮҢеҗҲгҒ„гӮ’иҝҪгҒ„гҒӢгҒ‘гӮӢгҖӮ зӢӯгҒ„д»®иЁӯдҪҸе®…гҒ®жҖҘгҒ”гҒ—гӮүгҒҲгҒ®д»ҸеЈҮгҒ®еүҚгҒ§гҖҒгҖҢд»Ҡж—ҘгҒ§1е№ҙгҒ§гҒҷгҖҚгҒЁз©ҸгӮ„гҒӢгҒ«еҫ®з¬‘гӮҖз”·жҖ§гҖӮд»ҸеЈҮгҒ«гҒҜгҖҒзҲ¶гҖҒжҜҚгҖҒеҰ»гҖҒеЁҳгҒ®4дәәгҒ®еҶҷзңҹгҒҢдёҰгӮ“гҒ§гҒ„гӮӢгҖӮеҪјд»ҘеӨ–гҒ®е®¶ж—Ҹе…Ёе“ЎгҒҢгҖҒи»ҠгҒ§йҒҝйӣЈгҒҷгӮӢйҖ”дёӯгҒ«жҙҘжіўгҒ«гҒ®гҒҫгӮҢгҒҹгҒ®гҒ гҖӮи»ҠгҒ®зҷәиҰӢжҷӮгҖҒгҖҢеЁҳгӮ’иғёгҒ«жҠұгҒ„гҒҰдҪ•еәҰгӮӮеҗҚеүҚгӮ’е‘јгӮ“гҒ гҒ®гҒҜиҰҡгҒҲгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖҚгҒЁиӘһгӮӢз”·жҖ§гҒҜгҖҒйӣ»ж°—еә—гӮ’е–¶гӮ“гҒ§гҒ„гҒҹгҖӮеҝғгҒ®дёӯгҒ§дёҖз·’гҒ«з”ҹгҒҚгҒҰгҒ„гҒҸгҒЁгҖҒж·ЎгҖ…гҒЁгҒ—гҒӢгҒ—жғігҒ„гӮ’иҫјгӮҒгҒҰиӘһгӮӢз”·жҖ§гҒҜгҖҒд»®еә—иҲ—гҒ§йӣ»ж°—еә—гӮ’еҶҚй–ӢгҒ—гҒҹгҖӮгҖҢд»Ҡж—ҘгҒ гҒӢгӮүгҒЁиӮ©иӮҳејөгҒЈгҒҰгҖҒгҒ•гҒӮгҒ“гӮҢгҒӢгӮүгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒҜз„ЎгҒ„гӮ“гҒ§гҒҷгҒ‘гӮҢгҒ©гҖҒеүҚгҒ«йҖІгӮҖгӮҲгҒҶгҒ«гҒ—гҒҹгҒ„гҒ§гҒҷгҖҚгҖӮ еңҹеҸ°гҒ—гҒӢгҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹ家гҖӮгҒ гҒҢгҖҒгҒқгҒ“гҒ«дҪҸгӮ“гҒ§гҒ„гҒҹж’®еҪұиҖ…гҒҜеұҲиЁ—гҒӘгҒҸгҖҒгҖҢгҒ“гҒ“гҒҢеҸ°жүҖгҖҒгҒ“гҒ“гҒҢгғ”гӮ«гғ”гӮ«гҒ гҒЈгҒҹе»ҠдёӢгҖҚгҒЁзҙ№д»ӢгҒҷгӮӢгҖӮеә§ж•·гҒ гҒЈгҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҒ«гҖҒгҒӘгӮ“гҒЁз•‘гӮ’дҪңгӮҠгҒ гҒ—гҒҹгҖӮе‘ЁгӮҠгӮ’иҰӢжёЎгҒ—гҒҰгӮӮгҖҒгӮ¬гғ¬гӮӯд»ҘеӨ–гҒ«гҒҜдҪ•гӮӮгҒӘгҒ„гҖӮеҪјеҘігҒҜгҖҢгҒ“гӮ“гҒӘйўЁжҷҜгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒгҒ„гҒӨгҒӢгҒҜжҲ»гӮӢгҒһпјҒгҖҚгҒЁе…ғж°—гҒ«еҸ«гҒ¶гҖӮ жңқгҒӢгӮүгғҸгӮӨгғҶгғігӮ·гғ§гғігҒ®еҘігҒ®еӯҗгҖӮзҲ¶иҰӘгҒҢж’®гҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгӮ«гғЎгғ©гӮ’гҖҢиІёгҒ—гҒҰгҖҒиІёгҒ—гҒҰгҖҚгҒЁйЁ’гҒҢгҒ—гҒ„гҖӮгҒҠе§үгҒЎгӮғгӮ“гҒҹгҒЎгҒҜиҝ·жғ‘гҒқгҒҶгҒ гҖӮеӨ–гҒ«еҮәгӮӢгҒЁгҖҒйҒ“и·ҜгҒ«е°‘гҒ—йӣӘгҒҢж®ӢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгӮ«гғЎгғ©гӮ’еҘӘгҒ„еҸ–гӮҠгҖҒиө°гӮҠеҮәгҒҷеҘігҒ®еӯҗгҖӮеҪјеҘігҒҢзҲ¶гӮ’е°ҺгҒ„гҒҹгҒқгҒ®е…ҲгҒ«гҒҜгҖҒйӣӘгҒҢи§ЈгҒ‘гҒҹеңҹгҒ®дёҠгҒ«гҖҒе°ҸгҒ•гҒӘе°ҸгҒ•гҒӘй»„иүІгҒ„иҠұгҒҢе’ІгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ дёҖи»’гҒ®е®¶гҒ®дёӯгӮ’гӮ«гғЎгғ©гҒ§жҳ гҒҷз”·жҖ§гҖӮеҰ»гҒЁеЁҳгҒҜйқҷеІЎзңҢгҒ«иҮӘдё»йҒҝйӣЈгҒ—гҒҰгҒ„гҒҰгҖҒгҒҠгҒЁгҒЁгҒ—гҒ®10жңҲгҒ«е»әгҒҰгҒҹ家гҒҜгҖҒгҒҫгҒ ж–°гҒ—гҒ„гҒҢдәәж°—гӮӮгҒӘгҒҸгӮ¬гғ©гғігҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҖҢйӣўгӮҢгҒҰгӮӮ家ж—ҸгӮ’е®ҲгҒЈгҒҰгҒ„гҒҚгҒҹгҒ„гҒӘгҒЁжҖқгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮеҰ»гҒЁеЁҳгҒЁгӮӮгҒҶдёҖеәҰдёҖз·’гҒ«дҪҸгӮҒгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮӢгҒ®гҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгҒӢгӮүгҒ®йЎҳгҒ„гҒ§гҒҷгҒӯгҖӮгҖҚгӮ«гғЎгғ©гӮ’еҲқгӮҒгҒҰиҮӘеҲҶгҒ«еҗ‘гҒ‘гҒҰгҖҒз”·жҖ§гҒҜгҖҢй ‘ејөгӮҠгҒҫгҒҷгҖҚгҒЁгҖҒйқҷгҒӢгҒ«гҒ‘гӮҢгҒ©гҒ—гҒЈгҒӢгӮҠгҒЁжӢігӮ’гҒӮгҒ’гӮӢгҖӮ |
|
|
|
гҒқгӮҚгҒқгӮҚгҖҒжҳјйЈҹгҒ®жҷӮй–“гҒ гҖӮй°»йҮҚгӮ’зҫҺе‘ігҒ—гҒқгҒҶгҒ«гҒӢгҒҚиҫјгӮҖз”·жҖ§гҖҒж–ҷзҗҶгӮ’жҗәеёҜгҒ§ж’®гӮӢиӢҘиҖ…гҖҒгҒқгҒ—гҒҰзҘ–зҲ¶гҒЁеӯ«еЁҳгӮүгҒ—гҒ„2дәәгҒ®еҶҷзңҹгҒ«гҖҒе„ӘгҒ—гҒҸдҫӣгҒҲгӮүгӮҢгӮӢйҷ°иҶів”Җв”ҖгҖӮ гҒқгҒ—гҒҰд»ҠгҖҒж–°гҒ—гҒ„е‘ҪгҒҢз”ҹгҒҫгӮҢгӮҲгҒҶгҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮзү№еҲҘгҒӘ1ж—ҘгӮ’з· гӮҒгҒҸгҒҸгӮҠгҖҒгҒқгҒ—гҒҰгҒҫгҒҹзү№еҲҘгҒӘжҳҺж—ҘгӮ’иҝҺгҒҲгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«в”Җв”ҖгҖӮ |
PRODUCTION NOTE
|
|
|
еҗҚеҢ гғӘгғүгғӘгғјгғ»гӮ№гӮігғғгғҲгҒ®гӮҪгғјгӮ·гғЈгғ«гғ»гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜжҷӮд»ЈгҒ®ж–°гҒҹгҒӘгӮӢжҢ‘жҲҰ гғӘгғүгғӘгғјгғ»гӮ№гӮігғғгғҲгҒҢиЈҪдҪңз·ҸжҢҮжҸ®гӮ’жүӢжҺӣгҒ‘гҖҒгӮұгғҙгӮЈгғіпҪҘгғһгӮҜгғүгғҠгғ«гғүгҒҢзӣЈдҝ®гҒ—гҒҹгҖҺLIFE IN A DAY ең°зҗғдёҠгҒ®гҒӮгӮӢдёҖж—ҘгҒ®зү©иӘһгҖҸгҒҜгҖҒжҳ з”»еҲ¶дҪңгҒ®е…ЁгҒҸж–°гҒ—гҒ„еҪўгӮ’з”ҹгҒҝеҮәгҒ—гҒҹгҖӮдҪ•еҚғдәәгӮӮгҒ®дәәгҖ…гҒҢжҠ•зЁҝгҒ—гҒҹжҳ еғҸгҒӢгӮүгҖҒдёҖжң¬гҒ®жҳ з”»гӮ’дҪңгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҖҒгҒҫгҒ•гҒ«гӮҪгғјгӮ·гғЈгғ«гғ»гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜжҷӮд»ЈгҒ«гҒөгҒ•гӮҸгҒ—гҒ„еҲ¶дҪңж–№жі•гҒ гҖӮгҖҢгҒ“гҒ®жүӢжі•гҒҜгҖҒжҳ з”»еҲ¶дҪңгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгӮ°гғӯгғјгғҗгғ«гҒӘдҪ“йЁ“гӮ’гҒҷгӮӢж©ҹдјҡгӮ’дё–з•ҢдёӯгҒ®дәәгҖ…гҒ«жҸҗдҫӣгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«дҪңгӮүгӮҢгҒҹгҖҚгҒЁгғӘгғүгғӘгғјпҪҘгӮ№гӮігғғгғҲгҒҜиӘ¬жҳҺгҒҷгӮӢгҖӮжҠ•зЁҝиҖ…гҒҜгҖҒиҮӘгӮүжҳ еғҸгҒ®дё»йЎҢгӮ’йҒёгҒігҖҒиӮ©гҒ®еҠӣгӮ’жҠңгҒ„гҒҰеҖӢдәәзҡ„гҒӘжҖқгҒ„гӮ„з§ҳгӮҒгҒҹж„ҹжғ…гӮ’гғүгӮӯгғҘгғЎгғігӮҝгғӘгғјгӮҝгғғгғҒгҒ§иЎЁзҸҫгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҮәжқҘгӮӢгҖӮ гҒ“гҒ®жүӢжі•гҒ§гҖҒгғӘгғүгғӘгғјгғ»гӮ№гӮігғғгғҲзҺҮгҒ„гӮӢгӮ№гӮігғғгғҲпҪҘгғ•гғӘгғјпҪҘгғ—гғӯгғҖгӮҜгӮ·гғ§гғігӮәгҒҜгҖҒд»ҠеәҰгҒҜBBCгҒЁе…ұеҗҢгҒ§гҖҺгғ–гғӘгғҶгғіпҪҘгӮӨгғіпҪҘгӮўгғ»гғҮгӮӨгҖҸгӮ’еҲ¶дҪңгҒ—гҒҹгҖӮеүҚдҪңгҒҢдё–з•ҢиҰҸжЁЎгҒ гҒЈгҒҹгҒ®гҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгҖҒгҖҺгғ–гғӘгғҶгғігғ»гӮӨгғігғ»гӮўгғ»гғҮгӮӨгҖҸгҒҜиҰҸжЁЎгӮ’зё®е°ҸгҒ—гҒҰгҖҒзҸҫд»ЈгҒ®иӢұеӣҪгҒ®ж–ҮеҢ–гӮ„дәәгҖ…гҒ®з”ҹжҙ»гӮ’еҲҮгӮҠеҸ–гҒЈгҒҹдҪңе“ҒгҒ гҖӮ гҒқгҒ—гҒҰ2012е№ҙгҖҒгғ•гӮёгғҶгғ¬гғ“гҒӢгӮүгҒ®е‘јгҒіжҺӣгҒ‘гҒ«гҒ“гҒҹгҒҲгҖҒгғӘгғүгғӘгғјгғ»гӮ№гӮігғғгғҲгҒҢдёүеәҰгҒ“гҒ®ж–№жі•гҒ«жҢ‘жҲҰгҒ—гҒҹгҒ®гҒҢгҖҒгҖҺJAPAN IN A DAY [гӮёгғЈгғ‘гғі гӮӨгғі гӮў гғҮгӮӨ]гҖҸгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮжқұж—Ҙжң¬еӨ§йңҮзҒҪгҒӢгӮү1е№ҙеҫҢгҒ®3жңҲ11ж—ҘгҒ®ж·ұеӨңгҒӢгӮү24жҷӮй–“гҖҒж•°еӨҡгҒҸгҒ®дәәгҖ…гҒҢиҮӘгӮүвҖңзӣЈзқЈвҖқгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰж’®еҪұгҒ—гҒҹгҖҒиҮӘ然гҒ§гғӘгӮўгғ«гҒ§йӯ…еҠӣзҡ„гҒӘжҳ еғҸгӮ’дёҖжң¬гҒ®дҪңе“ҒгҒ«д»•дёҠгҒ’гҒҹгҖӮ ж—Ҙжң¬гҒӢгӮүгҒ®жҳ еғҸгҒҢдё»гҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖҒжң¬дҪңгҒ®гӮӘгғӘгӮёгғҠгғӘгғҶгӮЈ гҖҺLIFE IN A DAYгҖҸгҒ«гӮӮжҗәгӮҸгӮҠгҖҒжҠ•зЁҝгҒ•гӮҢгҒҹгҒҷгҒ№гҒҰгҒ®жҳ еғҸгӮ’иҰігҒҰз·ЁйӣҶгҒ®гҒҹгӮҒгҒ®еҲҶеҲҘдҪңжҘӯгӮ’гҒҷгӮӢгғӯгӮ¬гғјгғҒгғјгғ гҒ®гғӘгғјгғҖгғјгӮ’еӢҷгӮҒгӮӢгҖҒж—Ҙжң¬дәәгӮ№гӮҝгғғгғ•дёӯеі¶зөөйҮҢгҒҜиӘһгӮӢгҖӮ гҖҢгҖҺLIFE IN A DAYгҖҸгҒЁгҒ®дёҖз•ӘеӨ§гҒҚгҒӘйҒ•гҒ„гҒҜгҖҒгӮ„гҒҜгӮҠж—Ҙжң¬дәәзӢ¬зү№гҒ®ж„ҹжғ…иЎЁзҸҫгҒ§гҒҷгҖҚгҖӮ дё–з•ҢдёӯгҒӢгӮүжҳ еғҸгҒҢжҠ•зЁҝгҒ•гӮҢгҒҹгҖҺLIFE IN A DAYгҖҸгҒ§гҒҜгҖҒгӮ«гғЎгғ©гҒ«еҗ‘гҒӢгҒЈгҒҰиҮӘеҲҶгӮ’гӮўгғ”гғјгғ«гҒ—гҒҹгӮҠгҖҒеҸӢйҒ”гӮ„家ж—ҸгҒЁгҒ®жҷӮй–“гӮ’жҳ гҒ—гҒҹгӮҠгҒӘгҒ©гҖҒгғЎгғғгӮ»гғјгӮёжҖ§гҒҢеј·гҒҸгҖҒиғҪеӢ•зҡ„гҒӘгӮӮгҒ®гҒҢеӨҡгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ«еҜҫгҒ—гҖҒжң¬дҪңгҒ§гҒ®ж—Ҙжң¬гҒӢгӮүгҒ®жҳ еғҸгҒҜгҖҒдёҖдәәгҒ§йўЁжҷҜгӮ’ж’®гӮӢгҒӘгҒ©гҖҒдәәзү©гҒҢеҶҷгҒЈгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„жҳ еғҸгҒҢеӨҡгҒҸгҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгғӯгӮ¬гғјгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒжң¬еҪ“гҒ«гҒ“гӮҢгӮүгҒ®жҳ еғҸгҒ§гҖҒж’®еҪұжҷӮгҒ®жҠ•зЁҝиҖ…гҒ®жғігҒ„гӮ’иҰіе®ўгҒ«дјқгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҒ®гҒӢгҒЁеҝғй…ҚгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—з·ЁйӣҶгҒҢйҖІгӮҖгҒ«гҒӨгӮҢгҖҒгҒқгҒ®еҝғй…ҚгҒҜжқһжҶӮгҒ«зөӮгӮҸгҒЈгҒҹгҖӮгҖҢдёҖиҰӢж·ЎгҖ…гҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒе®ҹгҒҜзҙ жҷҙгӮүгҒ—гҒ„зһ¬й–“гӮ„ж„Ҹе‘ігҒҢжө®гҒӢгҒідёҠгҒҢгӮӢжҳ еғҸгҒҹгҒЎгҒ«еҮәдјҡгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮйҖҶгҒ«гҖҒзӣҙзҗғгҒ§дҪ•гҒӢгғЎгғғгӮ»гғјгӮёгӮ’дјқгҒҲгҒҰгҒҚгҒҹгҖҺLIFE IN A DAYгҖҸгӮҲгӮҠгӮӮгҖҒгӮҲгӮҠгғ‘гғјгӮҪгғҠгғ«гҒӘдәәгҖ…гҒ®дё–з•ҢгҒ«иёҸгҒҝиҫјгҒҝгҖҒйқҷгҒӢгҒ«гҒқгҒ®дәәгҖ…гҒ®з”ҹжҙ»гӮ’иҰіеҜҹгҒ—гҖҒгҒқгҒ®ж—ҘеёёгҒ«еӯҳеңЁгҒҷгӮӢж„ӣжғ…гӮ„иғҢжҷҜгҒ«гҒӮгӮӢзү©иӘһгӮ’гӮҶгҒЈгҒҸгӮҠгҒЁзҗҶи§ЈгҒ—гҒҰгҒ„гҒҸгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҖҚгҒЁдёӯеі¶гҒҜжҢҜгӮҠиҝ”гӮӢгҖӮгҖҢж—Ҙжң¬гҒЈгҒҰгӮ„гҒЈгҒұгӮҠгҒ„гҒ„гҒӯгҖӮжө·еӨ–гҒ«дҪҸгӮҖжҲ‘гҖ…гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®иүҜгҒ•гӮ’ж”№гӮҒгҒҰе®ҹж„ҹгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ®гҒ§гҒҚгӮӢиІҙйҮҚгҒӘзөҢйЁ“гҒ§гҒ—гҒҹгҖҚ гғҶгғ¬гғ“гҒҢд»ҠгҖҒгғЎгғҮгӮЈгӮўгҒЁгҒ—гҒҰгӮ„гӮӢгҒ№гҒҚгҒ“гҒЁ ж—Ҙжң¬гҒ®гғҶгғ¬гғ“еұҖгҒ«гҒҜгҖҒз·»еҜҶгҒ§зҫҺгҒ—гҒҸгҖҒгҒӢгҒӨгғҖгӮӨгғҠгғҹгғғгӮҜгҒӘжҳ еғҸеҲ¶дҪңгҒ®ж–ҮеҢ–гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮгҒқгӮ“гҒӘж—Ҙжң¬гҒ®жҳ еғҸж–ҮеҢ–гҒ®дјқзөұгҒҢж–°гҒҹгҒӘгғҶгӮҜгғҺгғӯгӮёгғјгҒЁеҮәдјҡгҒҶгҒЁгҒҚгҖҒдё–з•ҢдёӯгҒ®дәәгҖ…гҒҢж„ҹеӢ•гҒҷгӮӢдҪңе“ҒгҒҢеҮәжқҘдёҠгҒҢгӮӢгҒҜгҒҡгҒ в”Җв”ҖгҒ“гҒ®дҪңе“ҒгҒ®дјҒз”»гӮ’гғӘгғүгғӘгғјгғ»гӮ№гӮігғғгғҲгҒ«жҢҒгҒЎиҫјгӮ“гҒ гғ•гӮёгғҶгғ¬гғ“гҒ®ж—©е·қ敬д№Ӣгғ—гғӯгғҮгғҘгғјгӮөгғјгҒҜгҖҒгҒқгҒҶиҖғгҒҲгӮӢгҖӮ гғ•гӮёгғҶгғ¬гғ“гҒҜгҖҒгҒ“гҒ®ж–°гҒ—гҒ„еҲ¶дҪңжүӢжі•гӮ’й§ҶдҪҝгҒҷгӮӢгҒ«гҒӮгҒҹгҒЈгҒҰгҖҒ2011е№ҙ3жңҲ11ж—ҘгҒ®жқұж—Ҙжң¬еӨ§йңҮзҒҪгҒӢгӮү1е№ҙеҫҢгҒ®вҖңгҒқгҒ®ж—ҘвҖқгҒ«з„ҰзӮ№гӮ’зөһгӮҠгҖҒдё–з•ҢдёӯгҒ®дәәгҖ…гҒЁз№ӢгҒҢгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зӣ®зҡ„гҒЁгҒ—гҒҹгҖӮйңҮзҒҪгҒ«гӮҲгӮӢжҙҘжіўгҒҢдәәгҖ…гӮ’е®№иөҰгҒӘгҒҸиҘІгҒ„гҖҒзҪӘгҒ®гҒӘгҒ„дҪ•дёҮгӮӮгҒ®е‘ҪгӮ’еҘӘгҒЈгҒҹгҖӮгҒқгӮҢгҒ§гӮӮгҖҒе°‘гҒ—гҒҡгҒӨз”ҹжҙ»гӮ’з«ӢгҒҰзӣҙгҒ—гҖҒжңӘжқҘгӮ’жұәгҒ—гҒҰи«ҰгӮҒгҒӘгҒ„дәәгҖ…гҒҢгҒ„гӮӢгҖӮгғ•гӮёгғҶгғ¬гғ“гҒҜгҖҒиҮӘеҲҶгҒҹгҒЎгҒҢгғЎгғҮгӮЈгӮўгҒЁгҒ—гҒҰзӮәгҒҷгҒ№гҒҚгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒ1е№ҙгҒҢзөҢгҒЈгҒҹд»ҠгҖҒз§ҒгҒҹгҒЎж—Ҙжң¬дәәгҒҢгҒ©гҒҶгӮ„гҒЈгҒҰжҡ®гӮүгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгҖҒгҒ©гӮ“гҒӘж„ҹжғ…гӮ’жҠұгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгӮ’дё–з•ҢгҒ«зҷәдҝЎгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ гҒЁиҖғгҒҲгҒҹгҖӮгҒ•гӮүгҒ«гҖҒгҒ“гҒ®дјҒз”»гҒ«еҸӮеҠ гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒдәәгҖ…гҒ«иҮӘеҲҶгҒҹгҒЎгҒ®еӯҳеңЁгӮ’иЁҳйҢІгҒ—гҖҒз”ҹгҒҚгҒҰгҒ„гӮӢиЁјгӮ’ж®ӢгҒҷе–ңгҒігӮ’ж„ҹгҒҳгҒҰгҒ»гҒ—гҒ„гҒЁйЎҳгҒЈгҒҹгҖӮ |
|
|
|
ж—ҘиӢұгҒҢгӮҝгғғгӮ°гӮ’зө„гӮ“гҒ гҖҒдҪ•еҚҒдёҮжҷӮй–“гҒ«гӮӮеҸҠгҒ¶иҶЁеӨ§гҒӘжҳ еғҸгҒЁгҒ®й—ҳгҒ„ жҲҗз”°гҒЁгғһгғјгғҶгӮЈгғігҖҒз·ЁйӣҶгҒ®гӮҜгғӘгӮ№гғҶгӮЈгғјгғҠгғ»гғҳгӮ¶гғјгғӘгғігғҲгғігҒҢгҖҒжҠ•зЁҝиҖ…15,000дәәгҒӢгӮүзҙ жқҗгӮ’еҸ—гҒ‘еҸ–гӮӢгҒЁгҒ„гҒҶд»»еӢҷгӮ’иІ гҒЈгҒҹгҖӮж—ҘиӢұеҗҲеҗҢгҒ®еҲ¶дҪңгғҒгғјгғ гҒ®жңҖеӨ§гҒ®йӣЈйЎҢгҒҜгҖҒиЁҳйҢІжҳ еғҸгҒ®ең§еҖ’зҡ„гҒӘйҮҸгҒ гҒЈгҒҹгҖӮгҒҷгҒ№гҒҰгҒ®жҳ еғҸгӮ’жҠҠжҸЎгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҖҒз”»жңҹзҡ„гҒӘгӮҝгӮ°д»ҳгҒ‘гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒҢй–ӢзҷәгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮгҒҜгҒҳгӮҒгҒ«жҳ еғҸгӮ’вҖңдәәгҖ…вҖқвҖңж„ҹжғ…вҖқвҖңе ҙжүҖвҖқвҖңжҷӮй–“вҖқвҖңеҮәжқҘдәӢвҖқгҒӘгҒ©еӨ§гҒҫгҒӢгҒ«еҲҶйЎһгҒҷгӮӢгҖӮж¬ЎгҒ«дәәгҖ…гҒ§гҒҜвҖңиөӨгҒЎгӮғгӮ“вҖқвҖң家ж—ҸвҖқвҖңжҜҚвҖқгҖҒж„ҹжғ…гҒ§гҒҜвҖңжіЈгҒҸвҖқвҖң笑гҒҶвҖқвҖңиҲҲеҘ®вҖқгҖҒе ҙжүҖгҒӘгӮүвҖңеӯҰж ЎвҖқвҖңжө·еІёвҖқвҖңйӣ»и»ҠвҖқгҒӘгҒ©гҖҒгҒ•гӮүгҒ«зҙ°гҒӢгҒ„гӮҝгӮ°гҒҢгҒӨгҒ‘гӮүгӮҢгӮӢгҖӮгҒ“гҒҶгҒ—гҒҰеҲҶйЎһгҒ•гӮҢгҒҹжҳ еғҸгҒ§гҖҒд»ҠеәҰгҒҜзү№е®ҡгҒ®дәәгҖ…гӮ„з’°еўғгҒ«з„ҰзӮ№гӮ’е®ҡгӮҒгҒҹгӮ·гғ§гғјгғҲпҪҘгғ•гӮЈгғ«гғ гҒ®ж•°гҖ…гӮ’ж§ӢжҲҗгҒ—гҒҰгҒ„гҒҸгҖӮиҰ–иҰҡзҡ„гҒӢгҒӨеҸҷжғ…зҡ„гҒӘе…ұйҖҡзӮ№гҒ®гҒӮгӮӢжҳ еғҸгӮ’гғ‘гғғгғҒгғҜгғјгӮҜгҒ®гҒ”гҒЁгҒҸз№ӢгҒҺеҗҲгӮҸгҒӣгҒҰгҒ„гҒҸгҖӮгҒқгҒҶгҒҷгӮӢгҒҶгҒЎгҒ«гҖҒдҪңе“ҒгҒ®йӘЁзө„гҒҝгҒҢиҰӢеҮәгҒ•гӮҢгҖҒгӮӘгғјгғ—гғӢгғігӮ°гҖҒдёӯзӣӨгҖҒгӮЁгғігғҮгӮЈгғігӮ°гҒҢжұәгҒҫгҒЈгҒҰгҒ„гҒҸгҖӮдёҖеәҰгғ•гғ¬гғјгғ гғҜгғјгӮҜгҒҢжұәгҒҫгӮӢгҒЁгҖҒгҒ©гҒ®гӮ·гғ§гғғгғҲгӮ’дҪңе“ҒгҒ®гҒ©гҒ®йғЁеҲҶгҒ«еҪ“гҒҰиҫјгӮҖгҒӢгҒ«ж°—гӮ’йҒЈгӮҸгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖӮгӮ·гғ§гғғгғҲгҒ®дёҖгҒӨдёҖгҒӨгҒҢдҪңе“ҒгҒ®з№ӢгҒҢгӮҠгҒ«еҪұйҹҝгӮ’дёҺгҒҲгӮӢгҒӢгӮүгҒ гҖӮ дҪңе“ҒгӮ’ж”ҜгҒҲгӮӢгҖҒдҪ•гӮӮгҒ®гҒ«гӮӮеҪұйҹҝгҒ•гӮҢгҒӘгҒ„еӯҗдҫӣгҒҹгҒЎгҒ®жҳ еғҸгҒ®еҠӣеј·гҒ• жҳ еғҸгҒ®дёӯгҒ§жңҖгӮӮеӨҡгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒҜгҖҒеӯҗдҫӣгҒҹгҒЎгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеҪјгӮүгҒ®ж—ҘеёёгҒ®е–¶гҒҝгҒҜиҮӘ然гҒқгҒ®гӮӮгҒ®гҒ§гҖҒдё–з•ҢгҒЁгғқгӮёгғҶгӮЈгғ–гҒ«еҗ‘гҒҚеҗҲгҒҶгҒқгҒ®е§ҝгҒҜгҖҒгӮЁгғҚгғ«гӮ®гғјгҒ«жәўгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮеӨ§дәәгҒҢгӮ«гғЎгғ©гӮ’ж§ӢгҒҲгҒҹзһ¬й–“гҖҒгҒ©гҒҶгҒ—гҒҰгӮӮиЈҪдҪңеҒҙгҒ®ж„ҸеӣігҒҢеҸҚжҳ гҒ•гӮҢгӮӢгҖӮгҒ гҒҢгҖҒйқўзҷҪгҒ„гҒ“гҒЁгҒ«гҖҒеӯҗдҫӣгҒҹгҒЎгҒҜгҒқгҒҶгҒ„гҒЈгҒҹе•ҸйЎҢгҒ«гҒҜе…ЁгҒҸеҪұйҹҝгҒ•гӮҢгҒҡгҒ«гҒ„гӮӢгҖӮеӯҗдҫӣгҒҹгҒЎгҒҜгҖҒж„ҹжғ…зҡ„гҒ«гҖҒжң¬иғҪзҡ„гҒ«гҖҒзӣҙж„ҹгҒ§иЎҢеӢ•гҒҷгӮӢгҖӮ гҒқгҒ®зөҗжһңгҖҒеҪјгӮүгҒҜдҪңе“ҒгҒ«еӨҡеӨ§гҒӘеёҢжңӣгӮ’дёҺгҒҲгҒҹгҖӮгҒӘгҒңгҒӘгӮүеҪјгӮүгҒ“гҒқгҒҢгҖҒдҪңе“ҒгҒҢжҺўгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢзҸҫд»ЈзӨҫдјҡгҒ®е•ҸйЎҢгҒЁгҖҒе®ҹйҡӣгҒ«жңӘжқҘгҒ§еҗ‘гҒҚеҗҲгҒ„гҖҒеҜҫеіҷгҒҷгӮӢдәәй–“гҒ гҒӢгӮүгҒ гҖӮеҲ¶дҪңгғҒгғјгғ гҒҜгҖҒеҪ“еҲқгҒҜеӯҗдҫӣгҒҹгҒЎгҒ®жҳ еғҸгҒҢеӨҡгҒҷгҒҺгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’жҮёеҝөгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒеӯҗдҫӣгҒҹгҒЎгҒҜдҪңе“ҒгӮ’гҖҒгҒӢгҒ‘гҒҢгҒҲгҒ®гҒӘгҒ„е‘ҪгҒ®ијқгҒҚгҒ§жәҖгҒҹгҒ—гҒҹгҖӮ иҝҪжӮјдҪңе“ҒгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒд»Ҡж—ҘгӮ’з”ҹгҒҚгӮӢз§ҒгҒҹгҒЎгҒ®зү©иӘһ гҖҺLIFE IN A DAY ең°зҗғдёҠгҒ®гҒӮгӮӢдёҖж—ҘгҒ®зү©иӘһгҖҸгҒҢиЁјжҳҺгҒ—гҒҰиҰӢгҒӣгҒҹгҒ®гҒҜгҖҒзү№еҲҘгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„1ж—ҘгӮ’еҸ–гӮҠдёҠгҒ’гҒӘгҒҢгӮүгҖҒе®ҹгҒҜзү№еҲҘгҒ§гҒӘгҒ„ж—ҘгҒӘгҒ©1ж—ҘгӮӮгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ гҒЈгҒҹгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—д»ҠеӣһгҒ®д»»еӢҷгҒҜгҒқгҒ®йҖҶгҒ гҖӮвҖңжӮІеҠҮгҒӢгӮү1е№ҙзӣ®гӮ’иҝҺгҒҲгҒҹж—ҘвҖқгҒЁгҒ„гҒҶзү№еҲҘгҒӘж—ҘгҒҢеҮәзҷәзӮ№гҒ гҒӢгӮүгҒ гҖӮж—Ҙжң¬еҒҙгҒ®гғҮгӮЈгғ¬гӮҜгӮҝгғјгҒ§гҒӮгӮӢжҲҗз”°еІігҒҜгҖҒзү№еҲҘгҒӘж—ҘгҒ®дҪ•ж°—гҒӘгҒ„ж—ҘеёёгӮ’жҸҸгҒҸгҒ“гҒЁгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒж„Ҹеӣізҡ„гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„иҮӘ然гҒӘзү№еҲҘж„ҹгҒ«жәҖгҒЎгҒҹдҪңе“ҒгҒ«д»•дёҠгҒ’гӮҲгҒҶгҒЁжҖқгҒЈгҒҹгҖӮгҖҢиҝҪжӮјдҪңе“ҒгҒ«гҒҜгҒ—гҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гӮӮгҖҒжҲ‘гҖ…гҒ®йҒёжҠһгҒ гҒЈгҒҹгҖӮзү©иӘһгҒ®гғҷгғјгӮ№гҒЁгҒӘгӮӢйғЁеҲҶгҒ«гҒҜжҙҘжіўгҒ®иў«е®ігҒҢгҒӮгӮӢгӮӮгҒ®гҒ®гҖҒж—Ҙжң¬гҒҢд»ҠгҒ§гӮӮеёёгҒ«жӮІгҒ—гҒҝгҒ«жҡ®гӮҢгҒҰгҒ„гҒҰгҖҒжӮІеҠҮгӮ’д№—гӮҠи¶ҠгҒҲгӮүгӮҢгҒҡгҒ«гҒ„гӮӢгҒ гҒ‘гҒ®еӣҪгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜжҸҸгҒҚгҒҹгҒҸгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖҚгҒЁиӘһгӮӢгҖӮ иӢұеӣҪеҒҙгҒ®гғҮгӮЈгғ¬гӮҜгӮҝгғјгҒ®гғ•гӮЈгғӘгғғгғ—гғ»гғһгғјгғҶгӮЈгғігӮӮгҖҒгҖҢжӮІеҠҮзҡ„гҒӘеҮәжқҘдәӢгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒгҒқгӮҢгҒ§гӮӮдәәгҖ…гҒҢдәәз”ҹгӮ’з”ҹгҒҚз¶ҡгҒ‘гҒҰгҒ„гҒҸе§ҝгӮ’иЎЁзҸҫгҒ—гҒҹгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮжҲ‘гҖ…гҒҜдәәгҖ…гҒҢжӮІеҠҮгӮ’еҝҳгӮҢгӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒеӣҡгӮҸгӮҢгӮӢгҒ®гҒ§гӮӮгҒӘгҒҸгҖҒзўәгҒӢгҒ«гҒқгӮҢгҒһгӮҢгҒ®дәәз”ҹгӮ’з”ҹгҒҚгҒҰгҒ„гҒҸе§ҝгӮ’дҪңе“ҒгҒ«гҒ—гҒҹгҒӢгҒЈгҒҹгҖҚгҒЁиӘһгӮӢгҖӮ |
STAFF
|
|
|
гғ»гғӘгғүгғӘгғјгғ»гӮ№гӮігғғгғҲ/иЈҪдҪңз·ҸжҢҮжҸ® |
зү№еҲҘи©ҰеҶҷдјҡгҒё10зө„20еҗҚж§ҳгӮ’гҒ”жӢӣеҫ…пјҒ
|
|
|
гҒӮгӮҢгҒӢгӮүдёҖе№ҙеҫҢгҒ®2012е№ҙ3жңҲ11ж—ҘгҖӮ |
|
|
|
гҖҺJAPAN IN A DAYгҖҖ[гӮёгғЈгғ‘гғі гӮӨгғі гӮў гғҮгӮӨ]гҖҸ |



![гҖҺJAPAN IN A DAYгҖҖ[гӮёгғЈгғ‘гғі гӮӨгғі гӮў гғҮгӮӨ]гҖҸ11жңҲ3ж—ҘпјҲеңҹпјүе…ЁеӣҪй Ҷж¬ЎгғӯгғјгғүгӮ·гғ§гғј](http://diamondblog.jp/provide/cinema/files/2012/10/photo1.jpg)
![гҖҺJAPAN IN A DAYгҖҖ[гӮёгғЈгғ‘гғі гӮӨгғі гӮў гғҮгӮӨ]гҖҸ11жңҲ3ж—ҘпјҲеңҹпјүе…ЁеӣҪй Ҷж¬ЎгғӯгғјгғүгӮ·гғ§гғј](http://diamondblog.jp/provide/cinema/files/2012/10/photo2.jpg)
![гҖҺJAPAN IN A DAYгҖҖ[гӮёгғЈгғ‘гғі гӮӨгғі гӮў гғҮгӮӨ]гҖҸ11жңҲ3ж—ҘпјҲеңҹпјүе…ЁеӣҪй Ҷж¬ЎгғӯгғјгғүгӮ·гғ§гғј](http://diamondblog.jp/provide/cinema/files/2012/10/photo3.jpg)
![гҖҺJAPAN IN A DAYгҖҖ[гӮёгғЈгғ‘гғі гӮӨгғі гӮў гғҮгӮӨ]гҖҸ11жңҲ3ж—ҘпјҲеңҹпјүе…ЁеӣҪй Ҷж¬ЎгғӯгғјгғүгӮ·гғ§гғј](http://diamondblog.jp/provide/cinema/files/2012/10/photo4.jpg)
![гҖҺJAPAN IN A DAYгҖҖ[гӮёгғЈгғ‘гғі гӮӨгғі гӮў гғҮгӮӨ]гҖҸ11жңҲ3ж—ҘпјҲеңҹпјүе…ЁеӣҪй Ҷж¬ЎгғӯгғјгғүгӮ·гғ§гғј](http://diamondblog.jp/provide/cinema/files/2012/10/photo5.jpg)
![гҖҺJAPAN IN A DAYгҖҖ[гӮёгғЈгғ‘гғі гӮӨгғі гӮў гғҮгӮӨ]гҖҸ11жңҲ3ж—ҘпјҲеңҹпјүе…ЁеӣҪй Ҷж¬ЎгғӯгғјгғүгӮ·гғ§гғј](http://diamondblog.jp/provide/cinema/files/2012/10/photo6.jpg)
![гҖҺJAPAN IN A DAYгҖҖ[гӮёгғЈгғ‘гғі гӮӨгғі гӮў гғҮгӮӨ]гҖҸ11жңҲ3ж—ҘпјҲеңҹпјүе…ЁеӣҪй Ҷж¬ЎгғӯгғјгғүгӮ·гғ§гғј](http://diamondblog.jp/provide/cinema/files/2012/10/photo7.jpg)